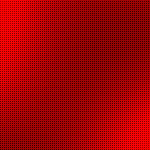ゲームPCとは、コンピュータゲームに特化したパソコンのことであり、様々なカスタマイズがされているものです。
特にアクションやシューティングのようなリアルタイムを主体といているゲームをいかに綺麗な画像でストレスなく動かせていけるかを考え、パソコンのパーツをそれぞれ高性能なものを選び組み立てたものです。
これは、ゲームを主体としたパソコンなので、趣味としてとらえられホビーパソコンの中に含まれています。
日本では1980年ごろに日立が初のホビーパソコンとなるMB-6880(ベーシックマスター)を発売しました。
それから、シャープがMZ-80Kを、NECがPC-8001をともに発売し、この2つでシュアを争いました。
この後に富士通がFM-8を発売し、NEC、シャープ、富士通の3社が揃いました。
FM-8に対抗するためにNECはPC-8801を発売することになりました。
1980年代後半になると富士通のFM-8の低価格版のFM-7が大ヒットしシャープを抜いて2位になりました。
しかし、NECのPC-8801を抜くことはできませんでした。
さらにシャープは対抗商品としてX1を開発、発売しこれによりシャープの主流がMZシリーズからX1シリーズに移行することになります。
市場はNECのPC-8800シリーズ、富士通のFM-7シリーズ、シャープのX1シリーズが大半を占めるようになり、この3社を「御三家」と呼ぶようになりました。
この競争に乗れなかったメーカーはMSXという統一規格を利用し参戦してきました。
これらの8bitパソコンに加え、NECはPC-9800シリーズの16bitも人気となりこれらでパソコンの市場を作っていきました。
パソコンの発売当初の価格は本体のみで188000円、これにモニターやその他周辺機器を合わせたら約60万円でした。
当時のゲームPCはNECのPC-6001、松下電器のMSX1/MSX2、コモドールのマックスマシーン、コモドールのコモドール64、カシオのPV-2000などがありました。
この他にオモチャのメーカーが発売していたものは、トミーのぴゅう太、バンダイのRX-78、セガのSC-3000、任天堂のファミリーベーシックなどがありました。
現在のゲームPCとして販売されているのは、パソコンのパーツをそれぞれ高性能のものを組み合わせたものが多く、特に3Dの描写に優れたものがよく売れています。
その分、総額が20万を超えるものが多いです。
最終更新日 2025年12月26日